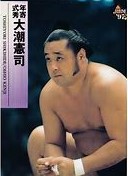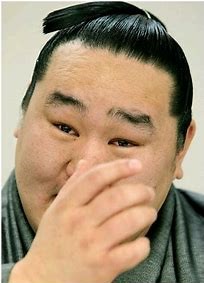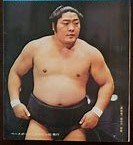昨日・おとといと2日連続で(相撲の)トークライブに出掛けてきました。
順におとといは埼玉県草加、昨日は東京・池袋と。
そこで記憶、印象に残った話題・ネタを紹介します。
25日の草加にて
いろんな忘れられないネタがありましたが、高田川親方の寛大さってところですかね。
アメとムチの使い分けが絶妙らしいんです!
所属力士全員に分け隔てなく声を掛ける。
⇈簡単にできることではないです。
「いいよ、いいよ」「絶対にこれを続ければ上に行けるよ!」「自信持ちなよ」
などなど、プラスに前向きな声掛けが次々に出てくるらしいんですよ。
かなりキツいことを言っても、必ずどこかでフォローがあるらしい(当然と言えば当然ですが)
(全員ではありませんが)中卒力士が多いのもこの部屋の特徴。親方なりのこだわりがあるみたいで。
親方の現役時代(殊勲インタビューなど)そこだけを取ると、不愛想・仏頂面(極端なまでの)無口など良い印象があまりなかったのですが、わからないものですね。

埼玉・草加にある居酒屋・闘勝花。気さくでおしゃべり大好きな元力士の店主が営む楽しいお店でした。
お店の情報です↓↓↓
https://tabelog.com/saitama/A1102/A110203/11033952/
26日・池袋編
「豊ノ島の部屋」と題したトークライブ。

豊ノ島とゲスト、3代目・若乃花でのやり取りの中で一番印象に残った(楽しい)話題は
(20年以上経ったから言えるが)若乃花が横綱在位時に7勝8敗で負け越した時のエピソード。
若乃花は当時の師匠(父でもある)貴ノ花に「引退します!」と即刻、その旨を伝えたが、師匠は「まだやるよな、まだやるよな」と3~4時間かけて強引にねじ伏せられたらしい(引退撤回をさせられた)とかで、千秋楽の打ち上げパーティーをやっているというのにそこを抜け出して、当時の理事長だった時津風理事長に2人で「現役続行」の意志を伝えに行った・・・の逸話があったそうだ(笑)
あと、現役の頃の若乃花は立ち合いの「待った」が比較的多かったが、そこで怒鳴りつける感じの鏡山審判(元横綱・柏戸)の注意は何を言っていたのかさっぱりわからなかったとのこと。会場がドッとウケてましたね。
NHKの中継画面でも、よくブチ切れた鏡山(柏戸)の姿は映し出されてましたが・・・(笑)

来年のカレンダーはいかがでしょうか↓↓↓