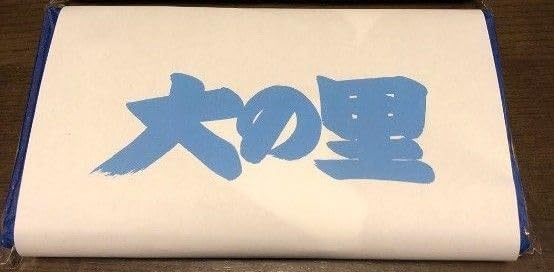十両の土俵でこんな素晴らしい珠玉の一番が見られた。若隆景に伯桜鵬。
両者、十両に留まるような力士ではない。
若隆景は右膝靱帯を中心とした大ケガで、3場所連続の休場。
伯桜鵬は左肩亜脱臼による2場所連続休場。
2人ともケガからの再起・復活への道のりを歩んでる途中である。
今場所ここまで
若隆景5連勝と突っ走り(内容が伴う・十分な稽古量を感じさせる)
伯桜鵬3勝2敗(一方的に負けたのは欧勝海戦のみ)
実際の取組を振り返る。
若隆景、やや低く頭からいく感じ。左四つで右上手を引いたようだ。
一度頭をつけて伯桜鵬の上体を起こし、苦し紛れになった伯桜鵬との投げの打ち合いになったが、若隆景の左からすくい投げが決まった。
7場所務めた元関脇がプロ経験の差を見せつけたか。
去年11月場所途中からの連勝が続いているそうでさすがですね。
この取組、もっともっと上のステージで、優勝(幕内)がかかる位置づけで見てみたいと思いました。
連勝記録をどこまで伸ばせるか、若隆景↓↓↓
若隆景 ミニタオル 応援タオル