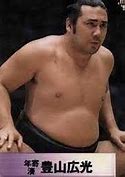北海の白熊こと元大関・北天祐。
入門時から大きな期待が寄せられ、「末は大関、横綱」「双葉山の再来」「未来の双葉山」とも称される。
またその端整なマスクから女性からの人気が高く、当時としては珍しく女性ファンから黄色い声援が上がっていた。

当時の北天祐ー千代の富士はホントにいい相撲・好勝負が多かった。
なぜか?どこまで本当かわからないが、理由や背景があったようだ。
ひとまず今日取り上げるこの取組は1985年7月場所13日目のものである。
時間前の痺れるような激しいにらみ合いから。
がっぷり四つでの力強い引きつけ合い、北天祐が千代の富士の上手を切りにいったり、外掛けを仕掛けたが未遂に終わる。最後は千代の富士が引きつけて勝負に出たところを踏ん張り、逆に力を溜めて豪快に吊り出してみせた。息をもつかせぬ白熱の一番だった。
ちなみにこの場所の優勝は、北天祐で13勝2敗の成績で挙げている。
この千代の富士戦の1勝で、対戦成績を(北天祐の)11勝12敗とするが、どういう訳かこの一番を機に千代の富士にほとんど勝てなくなった。北天祐・千代の富士の最終対戦成績は(北天祐の)14勝33敗となっている。
~北天祐の弟・富士昇~
さて、この二人の対戦が面白い相撲・いい勝負となる理由・背景の一部として挙げられることは・・・。
当時・北天祐の弟が九重部屋の力士だった。四股名「富士昇(ふじのぼり)」が千代の富士らを始めとする兄弟子連中が、富士昇に対して「かわいがり」の度が過ぎた版というか、殴る蹴るのプロレス技を駆使したとかで失明寸前までいったとか。
勿論、ここまでの事態に発展するには富士昇(北天祐弟)にも悪いところ・落ち度があるわけで。どうやら「生意気」「素行の悪さ」が重なったとされる。
知恵袋に書いてあったことを一部抜粋すれば、
富士昇(北天祐弟)は新弟子の頃から超の付く生意気だった。北天祐の弟をいい事に、門限破りや、大部屋での窃盗、親方への慣れ慣れしい態度は、兄弟子達の堪忍袋も限界に達して<か〇い〇り>に発展したと言われている。 事態はこれだけでなく、兄の後援会に金品をたかるなどしていました とあった。
そういった事が理由・背景とされて、北天祐は千代の富士戦に並々ならぬ闘志を燃やしていたとある。富士昇は、1982年7月場所限りで引退している。最高位は東三段目37枚目。現在の消息はわからなかった。
北天祐も千代の富士も鬼籍に入っている。
弟の件はさておき、この一番は熱狂した。何度見直しても手に汗握る。
北天祐が蘇る↓↓↓